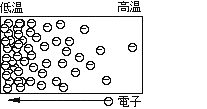
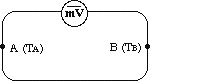
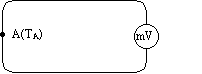
地中温度(地温)は、1日および1年を周期として変動する。その振幅(温度の変化幅)は深くなるにつれて小さくなり、その位相(最大値・最小値を示す時間)も深いほど遅れる。こうした現象は、気温や日射により地表面に流入した熱が、熱伝導によって地中に移動することによっておこる。
本実験では、土壌中に熱電対温度計を挿入し、地表面から周期的に熱を与えたときの地温変化を計測する技術を学ぶ。また、得られたデータから熱伝導率を求める方法について学習する。
温度を測る簡単な道具の一つに熱電対(thermocouple)がある。熱電対は用いる種類に応じて-200℃〜2000℃程度までの広い測定範囲をもち、比較的安価であること、遠隔測定ができること、測温部が小さいことなどの特徴がある。
熱電対は、その名の通り1対の金属線からなる。ある金属に温度差を与えると、金属内の自由電子が熱によって移動し高温側の密度が小さくなる(図-1)。このため、この金属の低温側は負に、高温側は正に帯電する。こうした自由電子の密度の変化は金属の種類によって異なる。そこで、2種類の金属線を図-2や図-3のようにつなぎ、接点A, Bに異なる温度を与えると、接点間に起電力(熱起電力)Eが発生することになる。この現象は発見者T. Seebeck (1821)にちなみ、ゼーベック効果と呼ばれる。
熱起電力の大きさは、金属がそれぞれ均質であれば金属線の組合せと接点間の温度差だけによって決まり、金属線の長さや太さ、接点以外の部分の温度などには無関係である。そこで、一方の接点を基準温度に保ち熱起電力を求めれば、もう一方の接点の温度が測定できる。銅−コンスタンタンの場合、1℃あたりの熱起電力はおよそ40μV(熱起電力1mVのときの温度差は25℃)である。
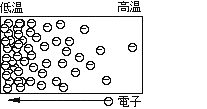 |
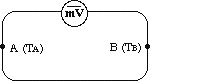 |
| 図-1 ある金属内の温度勾配下の電子密度 | 図-2 起電力の発生 (接点が2つの場合) |
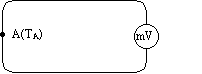 |
|
| 図-3 起電力の発生 (接点が1つの場合) |
土壌中における熱移動は、フーリエの法則によって表される。

|
(1) |
ここで、Jは熱フラックス(W/m2)、Tは温度(K)、xは距離(m)、λは熱伝導率(W/mK)である。
また、土壌中における熱の保存式は次式(2)で表される。
 |
(2) |
ここで、Hは次式で与えられる体積熱容量(J/m3)、rは体積あたりの発熱量(W/m3)、tは時間(s)である。
| H = C(T-Tref) | (3) |
ただし、Cは土壌の体積比熱(J/m3K)、Trefは基準温度である。r=0の場合、(2)式に(1)式と(3)式を代入し、Cを一定とすれば、次の熱伝導方程式を得る。
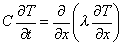 |
(4) |
さらに、λを一定と仮定すると、(4)式は次式となる。
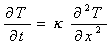 |
(5) |
ここで、κは次式で定義される熱拡散率(m2/s)である。
| κ = λ/C | (6) |
(4)式と(5)式に適当な境界条件や初期条件を与えると、解析解が得られる。ここでは、地表面に周期的な温度変化が与えられたときの解析解を考える。
いま、境界条件として
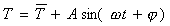 at x = 0 at x = 0 |
(7) |
 at x = ∞ at x = ∞ |
(8) |
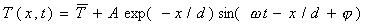 |
(9) |
ここで、
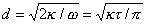 |
(10) |
| κ = πd2/τ | (11) |
(9)式より、深さxにおける地温の最大値、最小値、およびその差は次式となる。
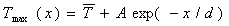 |
(12) |
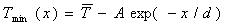 |
(13) |
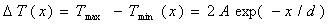 |
(14) |
ここで、2点の深さ(x1, x2)における地温の最大-最小の差を用いると、
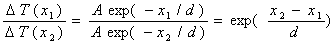 |
(15) |
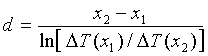 |
(16) |
(9)式において、深さxの地温は次式の関係を満たすとき最大となる。
| ωt - x/d + φ = π/2 | (17) |
ここで、2点の深さ(x1, x2)において地温の最大値を示す時刻を(t1, t2)とすると、
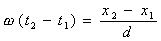 |
(18) |
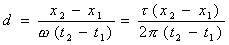 |
(19) |
(4)式と(5)式中のC、λ、κは一般的な物質であれば、熱的な性質を表す物質固有の定数である。しかし、土壌は土粒子、水、空気で構成されるので、その構成割合や配列などによってこれらの物性値が変化する。特に、水分量の影響を大きく受けることが土壌の熱物性の特徴である。
土壌の体積比熱は構成割合に基づいた次式により求められることが多い。
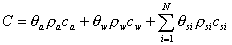 |
(20) |
ここで、θは体積分率、ρは密度、cは質量比熱、添字a, w, siはそれぞれ空気、水、土粒子成分を表す。通常、右辺第一項は他に比べて無視できるので、(20)式は次式のように簡略化できる。
| C = ρd (cs + cw w ) | (21) |
ただし、ρdは土壌の乾燥密度 (kg m-3; 単位系に注意)、wは含水比 (kg kg-1)、cs, cwはそれぞれ土粒子と水の質量比熱で、それぞれ840 (J/kg K)、4200 (J/kg K)である。
実測した地温変化から(11)式により決定する。
体積比熱と熱拡散率から(6)式を用いて算出する。


| 時間 t (min) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | ・・・ | 11.5 | 12 |
| 温度差 (1cm深) T1 | y0 | y1 | y2 | y3 | ・・・ | y24 | y25 |
| 温度差 (2cm深) T2 | z0 | z1 | z2 | z3 | ・・・ | z24 | z25 |
| 深さ (cm) | Tmax | Tmin | Tmax - Tmin | t (Tmax) |
| x1 = | t1= | |||
| x2 = | t2= |
| (16) 式 | (19) 式 | |
| d (cm) | ||
| κ (cm2/min) | ||
| κ (m2/s) |
| 物質 | 密度 (Mg m-3) | 比熱 (Mg m-3) | 熱伝導率 (W m-1 K-1) |
| 石英 | 2.66 | 0.80 | 8.80 |
| 粘土鉱物 | 2.65 | 0.90 | 2.92 |
| 有機物 | 1.30 | 1.92 | 0.25 |
| 水 (20℃) | 1.00 | 4.18 | 0.57 |
| 空気 | 0.0012 | 1.01 | 0.025 |
| 氷 | 0.92 | 1.88 | 2.18 |
解析解(9)の誘導のためのヒント
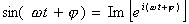 |
(22) |
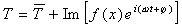 |
(23) |